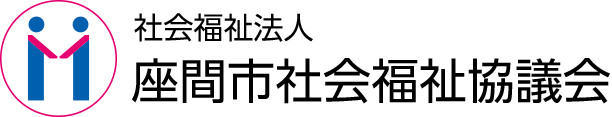令和6年度 社会福祉法人座間市社会福祉協議会 事業計画
令和6年度は、第4次座間市地域福祉活動計画の3年目となり、中長期的な地域の動向を見据え、地域福祉活動のあり方や既存事業の見直し、評価を進めるとともに、行政・福祉事業者や企業、そして住民と一丸となって、地域福祉の推進に取り組みます。
Ⅰ.<基本方針>~福祉の基盤づくりと組織管理体制の強化~
第4次座間市地域福祉活動計画の基本理念である「誰もが安心して暮らせる、ともに助け合い支え合うまちづくりを目指して」の実現に向けて、事業を実施します。
また、近年の多様な福祉施策・制度に対し、職員への教育研修を図りながら幅広い知識を身に付け、地域住民や行政との課題解決へのパイプ役を担えるよう、座間市の福祉の基盤づくりを推進します。
また、総合福祉センターの大規模改修工事に伴い、昨年度から約2年間、社協事務室が移転するため、社協各事業においてサービスを低下させることのないよう、組織管理体制を強化するとともに、関係機関・団体との連携を図ります。
Ⅱ.<第4次座間市地域福祉活動計画に基づく重点施策>
1.福祉まつりの内容・実施体制の見直し(担い手)・住民参加による福祉のまちづくり事業の推進
公共施設を有効活用し、市内の住民福祉活動と企業による社会貢献活動がつながり、一体的な福祉啓発と活性化を目的とした、新たな福祉まつりを実施します。
また、重層的支援体制整備事業を基軸に、高齢者/障がい者/子ども等の対象者を限定せず、 全ての人の福祉と接点が持てる事業を運営します。また、デジタル・ディバイド(情報格差)等に起因する福祉格差を解消するため、誰もが安心安全に地域でつながりが持てる取り組みを推進します。
主な事業
広報推進事業 福祉まつり運営事業 地区社協活動推進事業 子どもの学習・生活支援事業 居場所づくり推進事業
2.官民連携による福祉サービスの開発(居場所) ・団体や組織・行政と地域をつなげる中間支援機能を充実・強化
昨今の地域課題を調査・把握し、住民組織では解決が困難な課題を、官民連携のサービス事業により、地域全体で支え合う仕組みの構築に向けて、事業化を図ります。
また、地域共生社会の実現に向けて、地域包括ケアシステムによる生活支援体制整備、多職種連携、在宅医療・介護連携や、コミュニティースクール・社会福祉連携推進法人・農福連携といった、地域の様々な主体者が議論、検討などを行う協議の場の整理・運営を行い、有機的な連携による福祉推進を目指します。
主な事業
調査・研究事業 地域包括支援センター事業 ボランティアセンター運営事業 福祉活動助成事業 ネットワーク構築事業 生活支援コーディネート事業
3.社会福祉法人連携の推進(居場所・安心安全)
令和6年度も、上記2の官民連携による福祉サービスの開発を目標に掲げ、各法人の特性を活かした取り組みが地域課題の解決につながるよう、地域の共通課題を協議、検討を行う、法人間のネットワークを作ります。
主な事業
子どもの学習・生活支援事業 居場所づくり推進事業 生活支援コーディネート事業 ボランティアセンター運営事業 地域包括支援センター事業 ネットワーク構築事業
4.在宅支援サービス(居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション)の充実
当協議会職員の福祉専門職とする豊富な人材を活かし、利用者への適切なサービス提供と、事業経営の安定を維持するため、さらなる管理体制の強化を図ります。
主な事業
居宅介護支援事業 訪問看護ステーション事業
5.第4次座間市地域福祉活動計画の推進
座間市社会福祉協議会と地域住民や関係団体などが連携し、地域課題解決に向けた取り組みを組織的、計画的に推進し、実行するための行動計画です。
令和6年度は、計画の推進、評価見直しを進めるために、アンケート等を行い、現状把握による評価の視点を確立します。
活動計画重点項目 1.担い手づくり 2.居場所づくり 3.安心・安全な地域づくり
6.総合相談を推進
様々なネットワークを通じて相談者の最初の窓口を目指し、社会的包摂の視点からの困りごとの整理を行いつつ、適切な機関・支援へつないでいく包括的支援・伴走型支援を行います。
主な事業
日常生活自立支援事業 法人後見事業 成年後見利用促進センター事業 ファミリー・サポート事業 生活資金貸付事業 生活福祉資金貸付相談事業 家計改善支援事業 被保護者家計改善支援事業 子どもの学習・生活支援事業 地域包括支援センター事業 訪問看護ステーション事業 居宅介護支援事業
7.財源の確保
行政による財政支援はもとより、市社協自らも資金確保・ファンドレイジングに努めます。
また、地域福祉活動者も継続的に資金調達ができる仕組みを構築し、安定的な福祉活動の運営の一助となることを目指します。
主な事業
ボランティア活動推進事業 売店運営事業 自動販売機設置運営事業 善意銀行運営事業 基金運用事業
8.拠点設置とネットワークの強み事務局運営体制の強化
組織管理体制の見直しと内部研修の充実を図り、市社協の組織力の強化に努めます。
主な事業
法人運営事業 調査・研究事業
※用語の説明
用語(所轄庁等) 概要
重層的支援体制整備
(厚生労働省) 市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施することを必須にしています。
情報格差
(総務省) インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差のことをいう。具体的には、インターネットやブロードバンド等の利用可能性に関する国内地域格差を示す「地域間デジタル・ディバイド」、身体的・社会的条件(性別、年齢、学歴の有無等)の相違に伴うICTの利用格差を示す「個人間・集団間デジタル・ディバイド」、インターネットやブロードバンド等の利用可能性に関する国際間格差を示す「国際間デジタル・ディバイド」等の観点で論じられることが多い。
地域共生社会
(厚生労働省) 社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。
地域包括ケアシステム
(厚生労働省) 重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム
・生活支援体制整備 ・多職種連携 ・在宅医療・介護連携
コミュニティースクール
(文部科学省) 学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律(地教行法第47条の5)に基づいた仕組みです。
社会福祉連携推進法人
(厚生労働省) 社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。社会福祉連携推進法人の活用により、福祉・介護人材の確保や、法人の経営基盤の強化、地域共生の取組の推進などが可能
農福連携
(農林水産省) 障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組です。
農福連携に取り組むことで、障害者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性もあります。
地域福祉活動計画
(全国社会福祉協議会) 社会福祉協議会がよびかけて、住民、地域において社会福祉に関する活動を行うもの、社会福祉を目的とする事業(福祉サービス)を経営する者が相互協力して策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画です。
総合相談
(県社会福祉協議会) 本人等から社協の窓口に直接的に寄せられる相談に対して個別に対応することだけではなく、①地区社協等の住民活動、および専門職等とのネットワークからの地域の生活問題の把握②フォーマル・インフォーマルネットワークを生かした問題解決の取り組み③問題解決と予防のための地域づくりなど、問題の把握から解決と予防のしくみづくりまで含めたものであり、これを社協特有の機能、特性を生かして展開していくことをさしている。
社会的包摂
(厚生労働省) 問題が複合的に重なり合い、社会の諸活動への参加が阻まれ社会の周縁部に押しやられている状態あるいはその動態を社会的排除(Social Exclusion)と規定し、これに対応して、社会参加を促し、保障する諸政策を貫く理念として用いられるようになった。
包括的支援
(厚生労働省) 地域のケアマネジメントを総合的に行うために、介護予防ケアマネジメント、総合相談や支援、権利擁護事業、ケアマネジメント支援などを包括的に行う事業のことです。
伴走型支援
(厚生労働省) 支援者と本人が継続的につながり関わり合いながら、本人と周囲との関係を広げていくことを目指すもの
ファンドレイジング
(日本ファンドレイジング協会) NPO(民間非営利団体。NPO法人のみならず公益法人、社会福祉法人などを含む)が、活動のための資金を個人、法人、政府などから集める行為を総称していう。
総務課 法人運営係へのお問合せ
電話:046-266-1294
FAX:046-266-2009
受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(土日・祝日・年末年始を除く)
〒252-0021 神奈川県座間市緑ケ丘一丁目2番1号
サニープレイス座間